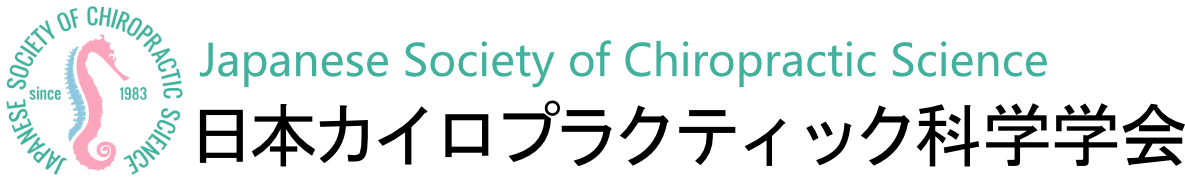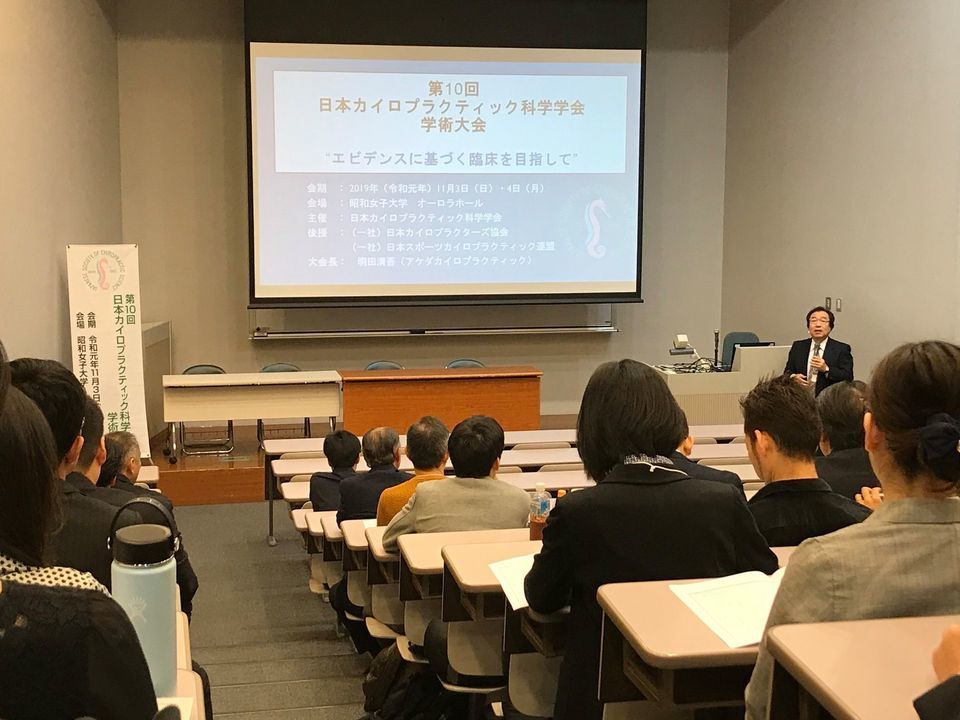
【会期】2024年6月16日(日)・17日(月)
【会場】オンライン学会(ZOOM利用)
【大会長】柴田泰之(医療法人社団プラタナス 株式会社メディヴァ スパイナルケア用賀 院長)
【テーマ】「地域医療を通して最善の健康を考える」
【主催】日本カイロプラクティック科学学会
【後援】(一社)日本カイロプラクターズ協会・(一社)日本スポーツカイロプラクティック連盟
【基調講演】
- (独)国立病院機構北海道医療センター副院長 伊東 学
- 島根大学医学部附属病院総合診療医センター長 白石 吉彦
- 桜新町アーバンクリニック院長 遠矢 純一郎
- 聖路加国際大学PCC開発・看護情報学准教授 射場 典子
- カイロプラクティックしもん院長/JAC会長 高柳 師門
- 厚生労働省医政局医事課 永岡 高行
【招待講演】パネルディスカッション
- 石谷ヘルスセンター院長 石谷 三佳
- TAI Chiropractic NYC院長 仲野 広倫
- True Health & Wellness内治療院 須藤 陽次郎
- 若槻カイロプラクティック院長/JAC常務委員 若槻 朋彦(司会)
大会長挨拶
大会長 柴田 泰之
医療法人社団プラタナス 株式会社メディヴァ スパイナルケア用賀 院長
今年の学術大会テーマは「地域医療を通して最善の健康を考える」です。日本は全ての国民が同水準の医療を受けられる国民皆保険制度を採用していますが、昨今の超高齢社会による労働力人口の減少から医療の地域格差が広がり、さらには高齢者医療費の増加に起因する現役世代の医療保険料負担増が社会問題となっています。こうした問題の解決策として予防医療や健康増進計画の促進、過剰医療の抑制など根本的な医療制度改革が喫緊の課題です。
本学術大会のテーマに含まれる地域医療には様々な定義があります。厚生労働省は医療制度改革のひとつとして地域医療構想を掲げ、各地域における2025年の医療需要と病床の必要量を高度急性期・急性期・回復期・慢性期という4つの医療機能ごとに推計し策定しました。地域医療構想は現状の医療制度を堅持したまま医療の需要と供給のバランスを調整する政策ですが、より長期的な視点から言えば、在宅医療の充実や医療従事者の多職種連携や業務範囲拡大を可能とし、医療従事者と患者の相互協力による地域社会に根ざした医療制度を実現するための施策が望まれます。
自治医科大学は地域医療を「地域住民が抱えるさまざまな健康上の不安や悩みをしっかりと受け止め、適切に対応するとともに、広く住民の生活にも心を配り、安心して暮らすことができるよう、見守り、支える医療活動である」と定義し、疾患中心のケア(Disease Centered Care)から人々中心のケア(People Centered Care)への移行を促しています。単に患者の疾病治療に限らず、地域住民の生活の質や社会とのつながりも考慮する患者参画型の人々中心のケアは、患者の医療に対する満足度を高めます。そうした意味から、本学術大会では地域医療を敢えてPeople Centered Careと英訳しました。
2016年、WHOは世界保健総会において統合的人々中心の保健サービス(IPCHS: Integrated People-Centred Health Services)フレームワークを策定し、疾病や医療機関を中心に設計された医療制度から人々のために設計された医療制度へと移行することで、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(全ての人が適切な予防、治療、リハビリ等の保健医療サービスを、支払い可能な費用で受けられる状態)に向けた各国の事業発展を支援するとしています。
国際的に普及しているカイロプラクティックは人々の機能回復や健康増進に役立つ補完医療(現代医療を補完する医療)であり、腰痛などの筋骨格系疾患に対する効果が研究により注目されています。法制化された国々では、カイロプラクターはプライマリケア医療従事者として人々中心のケアを実践する立場にあり、多職種連携による協働ケアが行われています。我々カイロプラクターが地域医療に貢献するためには、古典的なカイロプラクティック独自の言語を避けて多くの医療従事者が理解できる共通言語を使用することが重要です。
本学術大会は、地域医療や整形外科分野の専門家による基調講演や、在米邦人カイロプラクターの方々による招待講演、および会員による一般演題をオンライン配信で予定しています。当日参加ができない皆様には事前登録による動画視聴をご用意しております。今年から日本カイロプラクターズ協会会員以外にも、医療系国家資格取得者や日本カイロプラクティック登録機構(JCR)認定登録カイロプラクターも当学会会員として入会が認められます。ぜひ皆様の本学術大会へのご参加を心よりお待ち申し上げます。
1) 医療保険制度改革を考える【厚生労働省】
2) 地域医療構想【厚生労働省】
3) 地域医療とは【自治医科大学】
4) Integrated people-centred care【世界保健機関】
5) ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)【厚生労働省】
6) WHO global report on traditional and complementary medicine 2019【世界保健機関】
7) WHO guideline for non-surgical management of chronic primary low back pain in adults in primary and community care settings【世界保健機関】
基調講演
題目
講演者
所属
<内容>
題目
講演者
所属
<内容>
題目
講演者
所属
<内容>
題目
講演者
所属
<内容>
題目
講演者
所属
<内容>
招待講演
題目
講演者
所属
<内容>
一般演題(症例報告)
- 未定
【プログラム】
6月16日(日)
13:00-13:10 開会挨拶 第15回学術大会 大会長
13:10-13:20 学会代表挨拶
13:20-13:50 基調講演①
14:00-14:20 基調講演②
14:30-16:30 招待講演
6月17日(月)
10:00-11:00 基調講演③
11:00-12:00 基調講演④
12:00-12:40 基調講演⑤
12:40-14:00 昼休憩
14:00-15:00 基調講演⑥
15:00-15:30 一般演題(症例報告)
15:45 閉会
※14:00-16:00 途中休憩あり
【参加費】
■ 正会員 8,000円(オンライン参加)
■ 卒後1年 5,000円(オンライン参加)
■ 学生会員 無料(オンライン参加)
■ 非会員 12,000円(オンライン参加)
【抄録集】5月下旬に抄録集をPDFデータでお送りします。(参加費込)。印刷冊子をご希望の方は郵送でお送りいたします。(300円:郵送料および税込)
【お願い】
- パソコン画面上でのビデオや携帯電話での動画撮影、および写真撮影はご遠慮ください。ご了承の程よろしくお願いいたします。
【申し込み】申し込み締め切りは6月10日です。
【大会事務局】 日本カイロプラクティック科学学会事務局
東京都港区西新橋3-24-5-503 一般社団法人日本カイロプラクターズ協会内
電話 03-3578-9390 Email : info@chiropractic.or.jp
お申込みフォーム